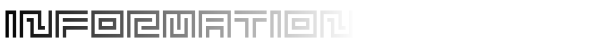02.04.02:40
[PR]
10.20.10:24
ブレード芯だし
ブレードの芯だしです。この辺をきちんと行わず適当にやっていたので、そこをプロに見破られた部分もあったかと思いますね。
青っぽく写っています部分が残っていますが、これが消えるまで削って芯を出していきます。
自分はかなり目が悪くなってしまい、感覚でやっていたのがいけなかったのかと思います。
ほんと付け焼刃と言いますけど、付け焼刃は駄目ですね。(笑)
押してってくれっけ。^^
PR
10.16.09:15
火床&ピザ釜製作記2
ピザ釜の口をアーチ型に作りました。
アーチの押さえ板は、レンガを地面に立てておきまして、開口部の長さをあわせて、レンガの下側がきっちりとあたるように調整します。
それを置いたレンガの上において、内側から鉛筆で転写しました。
上の写真は、モルタルが乾かないうちに押さえ板をはずしてしまって、ずれが生じてしまったので・・・。
硬化するまではずさないほうがよさそうです。自分は乾く前にはずしたほうが締るんじゃないかと思ったんですが、締るんですがずれの方がきつかったです。笑
隙間にモルタルを充填しましてアーチ完成です。
上の奥が開いてるのは煙突になる部分です。
一番難しいドームを積んでいきます。
レンガの数量を抑えるために立て積みにしました。そうすると積み方が難しいですね。
横からだとこんな感じです。中に見える金属のバーが傾斜確認のバーです。
これをまわしながら一個一個積んでいきます。
つっかえ棒を併用するんですが、1週積んでしまえばお互いが寄り添いますので大丈夫なんですよ。
つっかえ棒はせがれの竹刀の残骸がありますので良い長さに切って使用しました。
ここで、レンガがなくなったのでここまでです。
一気に購入しますと余ったりしてももったいないので順次購入します。支払いも分割になりますしね。笑
押してってくれっけ。^^
10.10.10:23
火床&ピザ釜製作記
土台が出来上がりましたので耐火レンガを敷いていきます。接着には耐火モルタルを使用です。
火床になる部分を作っていきます。火床の耐火レンガは3段積みにします。
火床の入り口部分をアーチ状にしていきます。
と思ったんですが、入り口をアーチ状にすると高さが3段増しになってしまうことがわかって急遽設計変更しました。
レンガの消費が著しいので、火床のアーチ化は断念しまして四角形です。
レンガの積層部が同じに重ならないように、レンガをカットしました。さらに5ミリぐらいの段になってしまったので、レンガ用のサンダーで面だしです。
横から見るとこんな感じです。
大判の耐火レンガを積みまして石釜の土台となります。後ろの部分の空きから、火床の熱を石釜に循環します。
3連休でここまで。さらに耐火レンガを購入しないといけません・・・。
結構な金額がかかりますね。すでに10万ぐらい消費しました・・・。
押してってくれっけ。^^
10.06.15:58
第33回 ナイフコンテスト受賞ならず
コンテスト事務局から案内が届きました。
こういう形で案内が来ることを知りませんでしたので、ちょっとびっくりでしたよ。
ちょっとドキドキしながら、受賞者一覧を見たんですが自分の名前はありませんでした・・・。
上には上がいる世界です。こういうところ好きです。
ナイフメーカーにとっては、文学の芥川賞、直木賞の類ですからそう簡単には受賞できません。
今回はナイフメーカーとしての免許証はもらえませんでしたけど、来年に向けてがんばって行きたいと思います。
まだ発表前ですので、受賞者名と作品名は伏せさせていただきました。
一般の方が奨励賞3名出ていますね。それ以外の方は会員様です。
一般で受賞できる方は凄いですね。もちろん、会員の方たちはそれ以上の実力者なんでしょうがね。
来年のコンテストに向けて切磋琢磨です。笑
ちなみに
今やっているインレイハンドルです。
アウトラインのエッジ部分、アウトラインといってもくりぬいた方のエッジ部分、インラインになるのかな?
この部分の整え方が少しわかってきました。
上がインラインを修正後で、下が修正前です。乱れが少なくなってると思います。
自分はグラインディングが致命的にヘタクソなので、その辺も切磋琢磨ですね。
来年に向けて。
今回出品作品です。クリックすると見えます。
押してってくれっけ。^^
10.03.09:58
火床製作記経過
セメントがほぼ固まっているように見えたので、木をはずして見たところ見事に粉砕・・・。笑
中はほとんど固まっていなかったので水を加えて直しました。
翌日のことです。せっかちは失敗の元です。笑
火床になるのは真ん中の四角い部分だけです。
左官は素人ですので出来上がるか心配ですね。笑
押してってくれっけ。^^