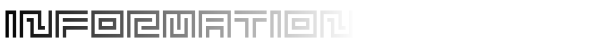02.15.06:17
[PR]
04.17.08:21
アルミ溶接で少しだけ分かったこと
つづくのログでなくてスイマセンです・・・。^^;
というのもパルスカバーの穴埋めを行う必要に迫られましてテストする必要があったためです。
フルコン化に伴いましてクランク角センサーをカスタムしたために、パルスカバーの予備品を作っておかないといけませんので・・・。
現行品はデブコンにて充填してありますがクラックなどの危険性を回避するためにも溶接の方が信頼線は高いですからね。
これはパルスカバーの切れ端です。
いきなり本品で行うには技術不足ですので切れ端でテストしました。
結果はご覧のとおり・・・。
本品でいきなりやらなくてホント良かったですね。^^;
アルミ鋳物の場合簡単にとろけてしまいました。
通常溶接の場合80A使っていたところを15Aまで下げましてもクニャクニャしてしまい溶接棒は溶け込まない感じでした。
アルミ鋳物の溶接は素人には超難関みたいですね。^^;
通常アルミ溶接で少しだけ分かったことです。
1.2.3の順に溶接を行っています。溶接部分は3ミリほどの段になっています。
アルマイト層が残っていますとトーチの火が飛び散ってしまい溶接できませんので、サンダーでアルマイトをはがしたんですが完全に剥離できていませんでした。
TIGの場合は酸化皮膜の除去と脱脂が改めまして重要であることがわかります。
酸化皮膜が残っているために火が安定せず溶接面も汚いですね。
2の部分も段になっている部分の酸化皮膜が残っていたために汚い溶接面です。
3の部分はだんの部分のアルマイトもはがしまして溶接しましたのでまあまあのビードになっています。
上の写真は溶接棒を送った時にトリタン棒に触れてしまったためです。
こうなるとご覧のように真っ黒のススのようなものが出てしまい、その後の溶接が汚くなってしまいます。
何度かやってみた結果、このような時は一度止めてステンブラシで磨いてから行ったほうが良さそうでした。
つなげてつなげて溶接したビードです。
自分の主観ですが溶接棒の溶け込みの輝きが綺麗なビードを引くコツのように思えます。
綺麗に輝いているビードの時は溶融池も輝いていまして、時には溶接棒の先端が写っていることもあるぐらいでした。溶接棒が溶融池以外で溶けてしまわないように、棒を送る時に若干トーチを後退させるようにして送るといい感じなようです。
その輝きを継続するにはやはりスピードとタイミングが欠かせません・・・。やはり練習あるのみでしょう。^^;
まだまだビード幅など不安定でまだまだですが頑張ります。^^;
溶接も奥が深いですね・・・。^^
Please click on one.
![]()
1日1回Please click
ブログ村の中からも記事をクリックしてくれるとランキングアップで嬉しいんですがねえ。^^;
PR
- トラックバックURLはこちら